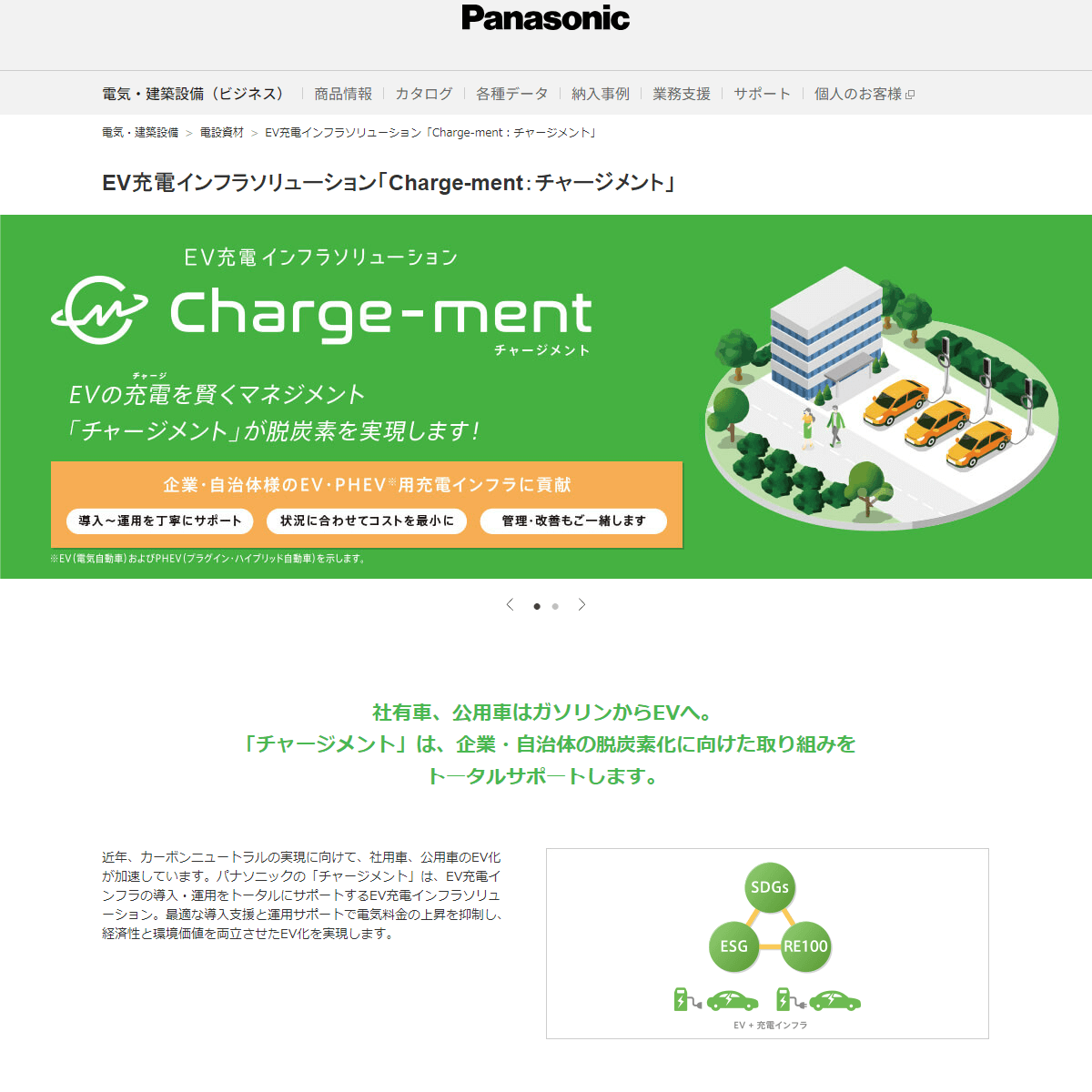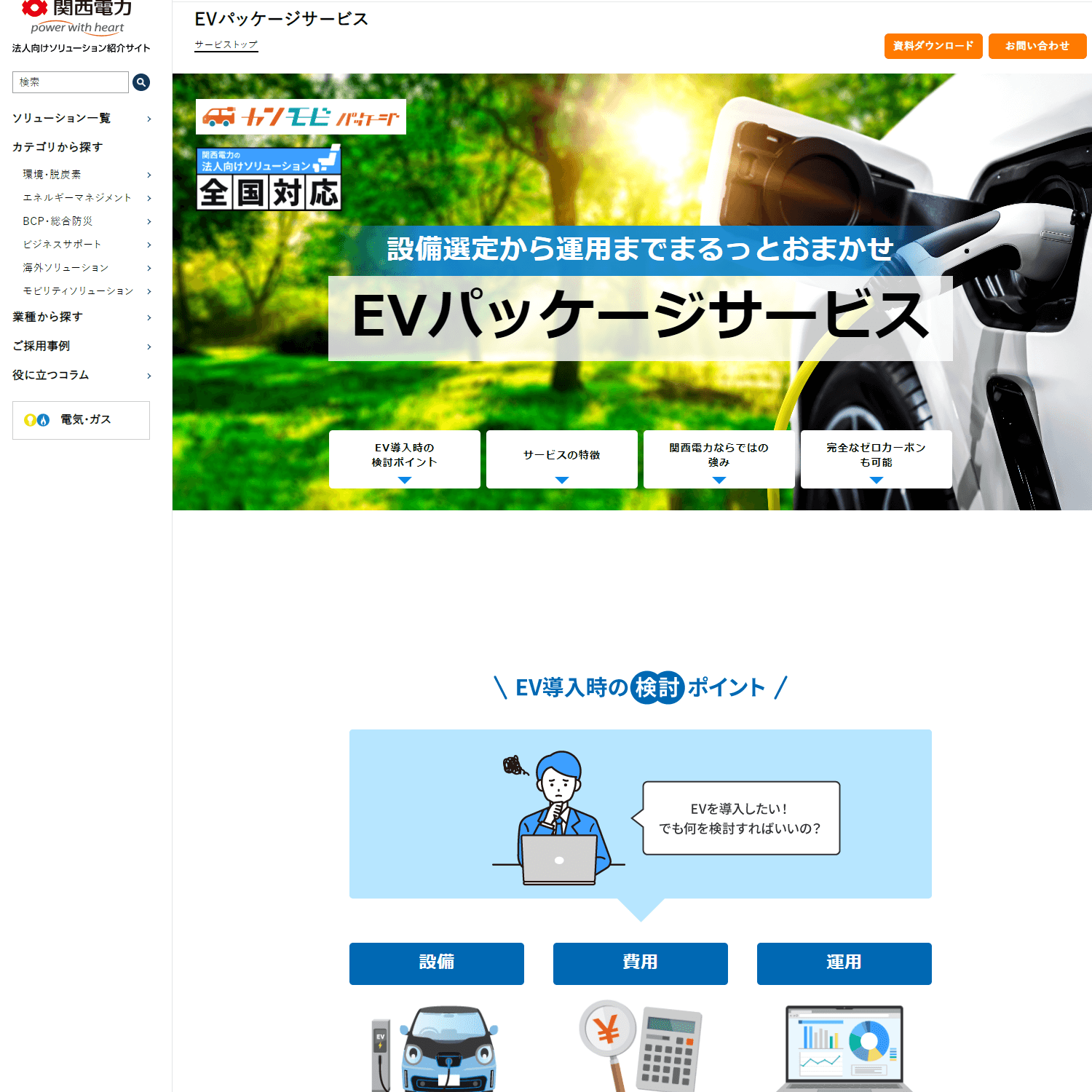電気自動車(EV)の普及に伴い、充電インフラの整備が注目を集めています。中でも「急速充電器」は、短時間でEVのバッテリーを充電できる点が大きなメリットとして評価されていますが、その仕組みや普通充電との違い、設置時の注意点について正しく理解できている人は意外と少ないかもしれません。本記事では、EVの急速充電の基本から普通充電との違い、利用シーンに応じた最適な使い分け、法人が導入する際のメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。導入を検討中の企業担当者やEVに興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
CONTENTS
おすすめのEV充電器設置導入サービスはこちら
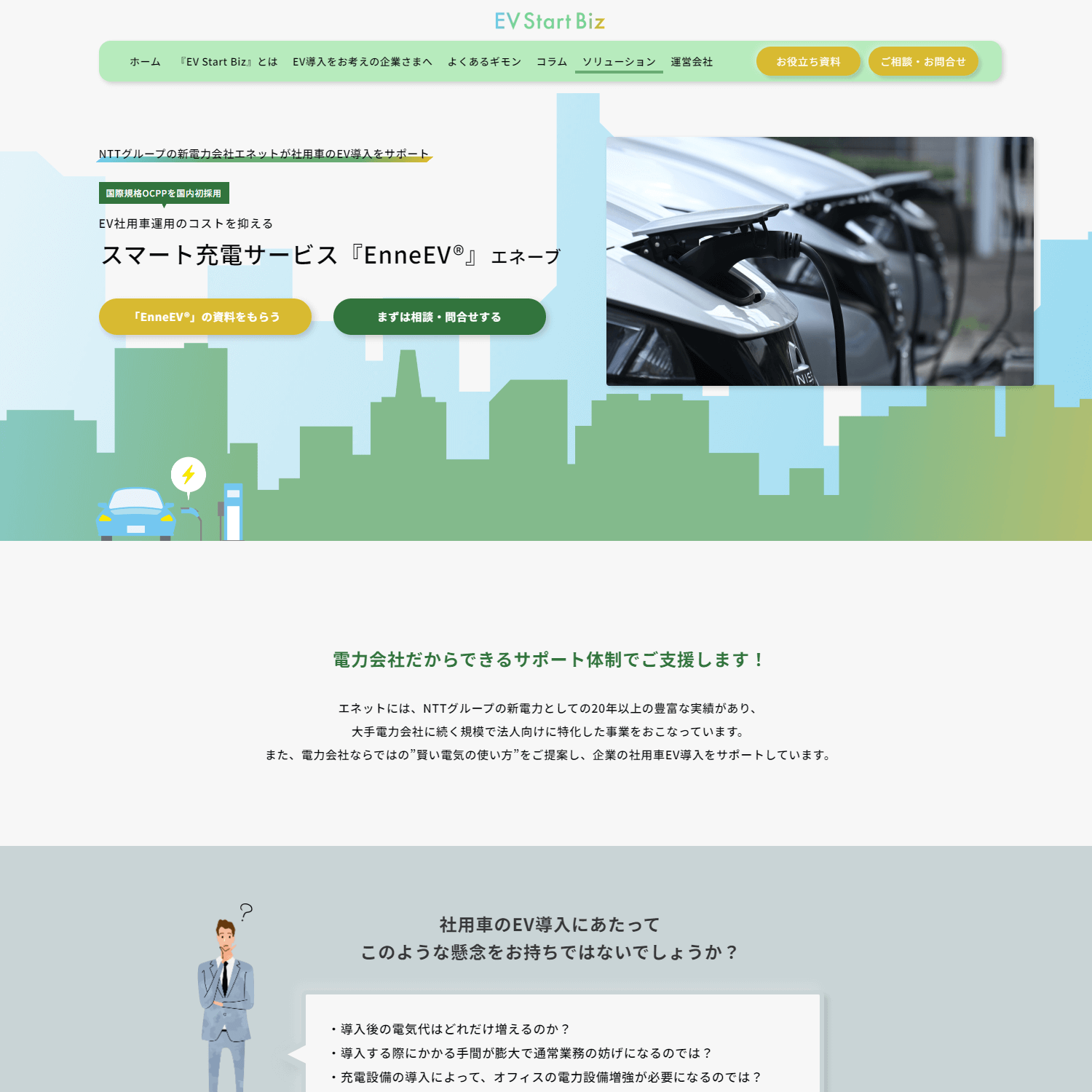
急速充電とは?仕組みと特徴をわかりやすく解説
EV(電気自動車)の普及が進む中で、短時間で充電を完了できる急速充電の存在はますます重要性を増しています。とくに業務車両や長距離運転が多い車両にとって、時間をかけずに電力を補給できる急速充電は、日常的な運用を支える大きなメリットとなります。
ここでは、急速充電の基本的な仕組みや特徴、どのようなケースで活躍するのかについてわかりやすく解説します。
急速充電とは?短時間での電力供給を実現する仕組み
急速充電とは、EVのバッテリーに短時間で大量の電力を流すことで、効率的に充電を完了させる方式です。出力は一般的に20kW〜90kW、場合によっては150kWを超えるタイプもあり、通常30〜60分程度で80%まで充電できるといわれています。
これは6〜8時間かかる普通充電と比べて大幅な時間短縮が可能で、この高速充電を実現するために、急速充電器は「直流(DC)方式」を採用している点がポイントです。家庭用の普通充電器が交流(AC)でバッテリー内のインバーターを通して変換しているのに対し、DC方式では直接バッテリーに電気を供給するため、変換ロスが少なくスピーディーな充電が可能になるのです。
主な急速充電の規格:CHAdeMOやCCSなど
急速充電には、主に3つの規格が存在します。日本国内で普及しているのは「CHAdeMO(チャデモ)」という規格で、これは日本の自動車メーカーが中心となって開発されたものです。出力の上限は150kW程度まで拡張されつつあり、多くの国産EVで採用されています。
一方、欧州車を中心に普及しているのが「CCS(Combined Charging System)」です。これは交流・直流の両方をひとつのポートでまかなえる仕様で、世界的に標準化が進んでいます。
なお、テスラ車は独自の「Tesla Supercharger」という高速充電ネットワークを構築していますが、近年ではCCSアダプターに対応するなど互換性の拡大が進んでいます。
どんな場所に設置されているのか
急速充電器は、主に「短時間での充電ニーズ」がある場所に設置されています。たとえば、高速道路のサービスエリアやコンビニ、ショッピングモールの駐車場、カーシェアスポットなどが代表的です。
また、企業が保有する営業車両や配送車向けに急速充電器を設けることで、業務の中断を最小限に抑えるケースも増えてきました。ただし、設置には高圧電源の確保や大規模な工事が必要になるため、住宅や小規模施設への導入はあまり一般的ではありません。
普通充電との違いは?どんな使い分けが理想的?
EVの充電方式には「急速充電」と「普通充電」の2種類があり、それぞれに特徴と適した利用シーンがあります。両者を単純に比較して優劣をつけるのではなく、車両の稼働時間や運用スケジュール、設置場所のインフラ状況などに応じて、最適な充電方式を選択・組み合わせることが重要です。
たとえば、24時間体制で車両が稼働する物流業や、遠方への営業が多い企業であれば、急速充電の導入が効果的です。一方で、オフィス勤務者が日常的に使用する社用車や、毎日の運行スケジュールが安定している車両であれば、普通充電を基本とした運用がコスト面でも利便性でも優れています。
ここでは、それぞれの特徴を深掘りし、法人が導入を検討する際に役立つ比較と導入指針を紹介します。
普通充電の特徴:低出力・長時間・コスト重視
普通充電は、主にAC(交流)を用いてEVの車載充電器を通してバッテリーを充電する方式で、出力は3kW〜6kW程度が一般的です。フル充電には6〜8時間と時間を要しますが、その分設備投資や電気工事のハードルが低く、コストも抑えられるのが大きなメリットです。
このため、自宅ガレージや企業の営業所、宿泊施設、公共施設など長時間駐車する場所に設置されることが多く、利用者の負担を最小限に抑えながら効率よく充電ができます。また、急速充電に比べて電力契約やピーク電力への影響が少ないため、電気料金の予測もしやすく、電力コストの管理面でも有利です。
急速充電と普通充電の「利用シーン」の違い
急速充電はDC(直流)を用いて高出力で一気に充電を行う方式で、30〜60分で80%程度の充電が可能です。長距離走行中の途中給電や緊急時の充電に非常に有効ですが、充電器本体や工事費が高額になりがちで、電気契約の見直しが必要な場合もあります。
これに対し、普通充電は時間に余裕のあるときにゆっくり充電する使い方が基本となります。たとえば、営業車を夜間事業所に戻して駐車しながら充電するといったケースでは、安価かつ確実に翌朝の満充電が確保できます。
このように、両者をうまく併用することで、法人でもEV運用の利便性と経済性を両立させることが可能です。
法人における「普通充電」導入の優位性
法人が初めてEV運用に乗り出す際、最も現実的で導入ハードルが低いのが普通充電器の設置です。導入コストは急速充電に比べて数分の一で済み、設置工事も比較的短期間で完了します。
社員が夜間に充電して翌朝から業務に使用する運用スタイルが確立できれば、急速充電に頼る必要がなく、トータルの運用コストを大幅に抑えることが可能です。また、国や自治体の補助金制度の対象にもなりやすく、賢く導入すれば初期費用をさらに軽減できます。
拠点が複数ある企業であっても、普通充電なら各拠点への分散導入も現実的で、事業規模に応じた柔軟な対応が可能です。今後EVの導入を検討する法人にとって、普通充電はコスト・安定性・拡張性の3点で非常にバランスの取れた選択肢といえるでしょう。
普通充電を導入する法人が増えている理由とは
法人がEV充電設備として「普通充電」を選ぶケースが増えています。主な理由は、初期費用とランニングコストが比較的安価で、導入しやすい点にあります。
普通充電は3kW~6kWの低出力で、数時間かけてじっくり充電するため、日中に車両を長時間停められる企業や施設に最適です。たとえば、社用車が夜間駐車場で充電する使い方に非常にマッチしており、運用の利便性が高いといえます。
また、政府や自治体の補助金制度でも普通充電器が対象となるケースが多く、補助金を活用して費用を抑えられる点も導入促進の大きな後押しとなっています。さらに、普通充電は設備規模が小さいため設置工事も比較的簡単で、短期間で導入できることも法人にとって魅力です。
EV充電設備選びは普通充電がコスト面でおすすめ
急速充電は短時間で充電できるため時間効率がよい利点があるものの、設備や工事費用が高額になりがちです。また高圧電源の整備が必要なことから、導入までの負担も大きくなります。さらに急速充電はバッテリーへの負荷が高く、長期的には劣化リスクも考慮が必要です。一方、普通充電は充電に時間がかかるものの、設置費用や維持費が抑えられ、補助金も利用しやすいことから法人での導入に適しています。長時間駐車中にゆっくり充電する運用であれば十分対応可能で、バッテリーにもやさしいため長持ちにもつながります。そのため、初期費用やランニングコストを抑えたい法人には、まず普通充電の導入がおすすめです。用途に合わせて適切に選び、将来的に急速充電を検討するのが賢明な選択といえるでしょう。